
「てくてく歩く」の記事で『貯蓄型保険』を何度かご提案させていただいております。
しかし、貯蓄型保険について書いた記事を作っていなかったので、素人ながら調べて考えて書くことにしました。
初めに「素人」と明かしたのには理由があります。
1つ目はそのままの意味で「素人」だという理由。
もう一つは「権威ではない」ということを強調しておきたかったからです。
私が調べたところ、「保険」には膨大な数の商品がありました。
「全部網羅するなんて無理!」と思い知らされたのです。(保険のプロの方、保険に携わる方を改めて凄いと思います。)
そして、私みたいなド素人が保険に入るのって、「実は相当大変なのではないか?」と思ったのです。
そこで素人が保険に加入する上でおそらく知っておいた方が良さそうな事がネット上にあるのではないかと考えて調べてみたのでご報告したいと思います。
もし、あなたにまとまったお金があって、保険加入を考えているのなら、とにかく保険のプロフェッショナルに相談することが1番のおすすめです。
しかし保険についていろいろな情報を聞く前に、基礎として知っておいた方が良さそうな『貯蓄型保険』のあれこれをまとめたので是非ご覧ください。
おそらく、加入相談する時にたくさんの初めての言葉を聞き、混乱してしまうことを防ぐくらいには役立つと思います。
 sora
sora

貯蓄型保険選びで確認すべきポイント


様々な情報が入ると『〇〇したらお金が増える』といったことが気になりだしてしまうのではないでしょうか?
なんの予備知識もなく保険の無料相談などに行くのは何となく怖いですよね。
私は説明を聞いても緊張してしまい理解できないままに加入してしまうような気がしてしまいます。
まず私が気になってしまうのは保険を検討する時に何を考えて何を確認した方が良いのかという点です。
そこで、はじめに貯蓄型保険選びで確認するべきことを見ていきたいと思います。



貯蓄型保険の特徴を確認
貯蓄型保険の特徴を確認しておきましょう。
この後詳しく貯蓄型保険についてどんどん書いていきます。
この時点では貯蓄型保険とは『いざという時の備え(保険)といつか〇〇〇〇する時に必要になるたくわえ(貯蓄)を同時に兼ね備えた保険』という感じでとらえておけば良いと思います。
いろいろな情報が一気に入ってい来ると「保険」と「貯蓄」のはずが、「投資」や「運用」といった要素が絡んでいるように感じませんか?
そして、最後には得なのか、損なのか…といった考えが浮かんできてしまうのではないでしょうか。



まずはシンプルに『いざという時のための保険+簡単に引き出せない貯蓄』ということを頭に入れておくことが大事ではないでしょうか。
あなたの貯蓄の目的を確認
もし貯蓄型の保険に加入するとしたら何のためにあなたは貯蓄をしたいのでしょうか?
老後の資金の準備のためですか?
お子様がいる場合には、お子様の教育費を準備するためかもしれませんね。
あるいは自分が老後、定期的に年金みたいにお金を毎月使えるようにするためかもしれません。
保険の特徴の1つとして、それぞれの保険の契約時の補償目的とは違う理由で保険金がもらえないという側面があります。
貯蓄型保険は契約途中で解約ができないということはないのですが、保険金支払期間中に解約すると支払った保険料全てを契約返戻金(解約返戻金)として受け取れないことが多く、損をしてしまうのです。
解約返戻金(かいやうへんれいきん)とは
貯蓄型保険の解約時に保険会社から戻ってくるお金のことをいいます。





返戻率(へんれいりつ)を確認
貯蓄型保険の話をすると、返戻率(へんれいりつ)の話がおそらくのぼってくると思うのですが、難しい数字の事になると窓口で頭が真っ白になってしまいませんか?
私は数字や〇〇率というような話になってくるとかなり混乱してしまうクチです。
返戻率とは
支払った保険金に対してなん%のお金が解約時に戻ってくるのかという比率を表します。
例えば…
保険支払期間中に合計で1千万円の保険金をした羅った時に解約時に戻ってくる保険料の金額が1千100万円だったとするとその返戻率は110%ということです。
戻率(%)=[解約時受取総金額]÷[払込保険料総額]×100
この例を計算式にあてはめると、1100万円÷1000万円×100=110となるので返戻率は110%となります。
保険のパンフレットなどに返戻率は記載されているとは思いますが、自分でもだいたい10年後の返戻率、15年後の返戻率、20年後の返戻率、支払期間満了時の返戻率といった具合に知っておくことも大事でしょう。



支払い完了時、満期に返戻率がどうなっているかを確認して納得してから保険に入るようにしたいですね。
保険料の支払いが可能か確認
貯蓄型保険の特徴として、支払い期間が短い保険はほとんどないようです。
また掛け捨ての保険と比べて保険料は割高になっています。
これは同じ保障額であっても保険料が掛け捨ての保険より貯蓄型保険の方が高いという意味です。
その高めの保険料を20年以上の長期にわたって払い続けることが可能かどうかよく検討する必要がありそうですね。
貯蓄型保険と掛け捨て保険の違い
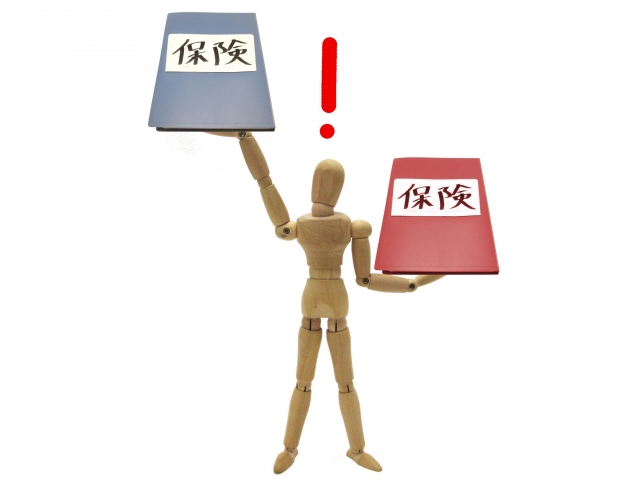
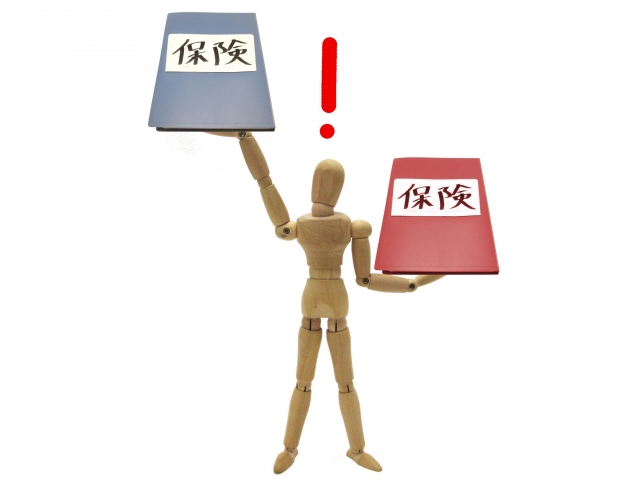
保険の基礎知識になりますが、保険は貯蓄型保険と掛け捨て保険と2つに分けることができます。今回は貯蓄型保険についてのお話をさせていただいています。
貯蓄型保険の特徴は保険の機能と貯蓄の機能をあわせもっているということ、いわば二刀流の保険といえるのではないでしょうか。
掛け捨ての保険との大きな違いは解約時や支払期間完了後に解約返戻金という、支払った保険料に対して保険商品の返戻率に応じた金額を受け取れるところになります。
先ほどもお伝えしましたが、貯蓄型保険の保険料は掛け捨ての保険と比べると同じ保証内容でも毎月支払う保険料が高いです。
最後に、掛け捨ての保険は保険支払期間も保障期間もある一定期間で見直すことができるのに対して、貯蓄型保険は掛け捨ての保険よりも長い期間同じ保険料を支払い続けるような商品が多くなります。
まとめると…
| 貯蓄型保険 | 掛け捨ての保険 | |
| 保険の目的 | 保険と貯蓄の二つを目的とした保険 | 万が一の時の保障を目的とするシンプルな保険 |
| 解約返戻金 | 返礼率に応じた額をもらえる | もらえないか、非常に少ない |
| 保険料 | 割高 | 安め |
| 支払い期期間 | 長期 | 短期から長期の保険商品があり、様々 |
| 保証期期間 | 長期 | 短期から長期の保険商品があり、様々 |
主な貯蓄型保険の種類


貯蓄型保険の種類は結構限られていて、主に死亡(終身)保険、養老保険、学資保険、個人年金保険の4つです。
他にはちょっと変わったものとして外貨建て保険や変額保険という保険もあります。
それぞれの保険について詳しく調べたので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
死亡(終身)保険
死亡(終身)保険はその名の通り死亡リスクに備えた保険です。
被保険者が死亡したり、高度障害状態になると保険金が支払われる仕組みになっています。
保険契約期間は一生涯にわたる保険となり、解約するとその時の返戻率で解約返戻金をもらうことができるとのことです。
解約返戻金は多くの場合契約開始時点から長期になるにつれて増えていき、保険料支払期間満了時を超すと返戻率が100%以上になる事が多いです。
低解約返戻金型終身保険という保険タイプもあります。
このタイプの保険は支払期間中に解約すると返戻金が大幅に減るけれど、保険料が抑えれるという特徴を持った貯蓄型終身保険です。



学資保険
あなたが一人暮らしをしていて、離れて暮らしているお子様が居れば、親としては将来のお子様の教育資金の備えをしておきたいですよね。
ですから、この記事では貯蓄型保険の学資保険についても触れます。
学資保険は契約時に定めたお子様の年齢(例えば18歳)になったら保険金が受け取れる仕組みになっている保険です。
この学資保険には保険料を払っている親が保険期間中に死亡などをしてしまった場合に保険料が免除されつつも契約した時の保険金を受け取ることができる特約を付け加えることができます。



更に契約する保険によっては、お祝い金がお子様の入学や進学時に受け取ることができます。


養老保険
養老保険とは被保険者が死亡した場合は死亡保証を受け取れるという点ではほぼ終身保険と変わりません。
終身保険と違うところは『被保険者が生存して満期を迎えた場合は満期保険金を受け取ることができる』という点です。
保証が一生涯続く死亡(終身保険)とはここが違います。



個人年金保険
個人年金保険は、個人で行政や団体などに頼らずに自分で年金を用意する保険です。
契約時に保険料支払期間を設けて毎月保険料を保険会社に積み立てていきます。
保険支払期間満期まで積み立てた金額を年金原資と呼び、これを契約時に決めた年齢から年金のように一定額ずつ定めた金額を決まった期間や生涯にわたり受け取れるという仕組みの保険です。
この貯蓄型保険には定額型と変額型があり、定額型は契約時に決めた金額を変額型は保険会社の運用実績によって変動した金額を受け取れる仕組みになっています。
被保険者が死亡した場合にも遺族年金のようにある一定の金額を年金方式で遺族に支払われるため、まとまった資金にはならない点も他の貯蓄型年金との違いになります。



死亡(終身)保険との違いはこの保険金の受取方法が、年金のように少額を毎月受け取る方法だという点です。
外貨建て保険
外貨建て保険とは外国の通貨で保険料を支払ったり保険金を受け取ったりする保険のことです。
貯蓄型保険の外貨建て保険は長期的に見て日本円がその外国通貨に対して今後円安に推移するのか、円高に推移してしまうのかを見通して加入する必要があります。
例えば、外国通貨(例えばUSドル)に対して円高から円安に推移するならばかなりの利益が見込めるでしょう。
現在(2022年6月9日)時点では、大幅な円安と言われていますが、将来これ以上の円安に推移していくと考えられるのであれば利益を見込むことができます。
しかし、現時点で歯止めがかかり、将来的にはもう少し円高に推移していくと考えるあれば損失につながるので、別の国の通貨や外貨建て保険ではない一般的な貯蓄型保険の方が良いでしょう。



変額保険
変額保険とは支払った保険料の一部を保険会社が運用し、その実績によって支払われる保険金や解約返戻金が増えたり減ったりする保険です。
この変額保険では、死亡した時の保険金には最低保障があります。
この保証は契約する時に決めた最低の保険金額を保証するもので、その金額より死亡保険金受取金額が下回ることがないことが保証されているのです。
しかし、死亡保障以外の保険金や解約返戻金は高くなることも低くなることもあるので、元本割れと言って支払った保険料の総額が戻ってこない可能性もあり、リスクが否めない貯蓄型保険となります。
保険の種類は主に有期型、終身型、年金型の3つです。
有期型の変額保険:死亡保障期限を定めてある保険
終身型の変額保険:保障期限が生涯続く保険
年金型の変額保険:年金のように保険金を受け取ることができる保険
貯蓄型保険のメリット


当然ながら貯蓄型保険にはメリットがあります。
この記事の初めに貯蓄型保険とは保険と貯蓄の2つの顔を持つ二刀流の保険だとお伝えしました。
メリットはまさにこの2つの顔、保険でいざという時に備えると同時に貯蓄で将来的に解約返戻金を使って資金として活用できることです。
簡単にいうと、『契約期間中は保証が約束されていて、解約する時に返戻金を使ってその後の生活の資金やライフイベントの資金として活用することができる。』ということになります。
他にもにもメリットがあるので見ていきましょう。
解約の時に返戻金がある
まずは解約の時に返戻金があるというメリットについてお伝えします。
貯蓄型保険は契約からある程度の期間が過ぎてしっかり保険料を払っていれば、保険加入時の保険商品の元々の目的以外であっても解約した時に支払った保険料の一部が戻ってくるのです。
具体的な例をあげましょう。
あなたが貯蓄型の死亡保険に入っているとしましょう。
そしてあなたのご家族の誰かが大病を患ってしまい、医療費の工面がどうしても必要だとしますね。
そんな時、この貯蓄型の死亡保険を解約したら解約返戻金の受け取りができます。
それまで支払った保険料の合計金額全額とはいきませんが、その時の返戻率で計算された額をご家族の医療費の資金に活用することができるのです。



解約返戻金はこのように『突然資金繰りに困った時に解約すればもらえる』という点が貯蓄型保険のメリットです。


ライフステージに合わせて活用可能
例えば学資保険は代表的な貯蓄型保険です。
まさにお子様のライフステージの変化である入学や進学といった人生の岐路が起きるたびにお祝い金が出る保険商品があります。
大学入学や社会人になるなどのライフステージの変化に照準を当てて契約することができ、満期になれば満期保険金をもらうことができる保険です。
この時、保険金をそこまで使わなかったときにはその後の生活資金として活用することもできます。
老後資金の準備にあてられる
貯蓄型保険のメリットとして1番分かりやすいメリットをお伝えします。
保険金を受け取る必要がなかった(例えば死亡保険に入ったが死亡していない)場合、保険料の払込が済んでしまえば支払った金額以上の解約返戻金を受け取ることができるのです。
終身保険などの場合はそのまま死亡保障が生涯続くので保険を解約せずに残すこともできます。
他にも、老後の生活資金や余暇を楽しむ資金として活用することも可能です。



自動振替貸付や契約者貸付ができる商品がある
自動振替貸付とは
保険料の支払いが銀行口座の引き落としでできなかった場合に、保険会社から貸付を受けることができ、一時的に保険料を借りて保険を継続することができるという貸付制度。
この自動振替貸付は契約者貸付制度に属する貸付になります。
契約者貸付制度は簡単な手続きで借入が可能ですが、利息を含めて返済が必要になるものです。
加入する保険によっては利用できなかったり金利が契約時の予定利率によって変わったりするので利用する時には注意してくださいね。
ミスで保険料の引き落としがなかったときにすぐに保険が失効されないというのがこの制度の利点です。



しかし、これは維持時的な措置で、一定期間を経過すると保険が失効するのでここも注意が必要みたいですよ。
生命保険料控除で節税が可能
生命保険料控除という課税所得の控除を受けることができます。
簡単にいうと、所得税と住民税を節税できるというメリットです。
1年間支払った保険料から算出した一定金額をその年の年収から差し引く仕組みになります。
所得が多くて税率が高い場合には課税対象となる年収(所得)が減るのでその分、税金が減るという大きなメリットです。
この生命保険料控除は貯蓄型生命保険でも、掛け捨て型の生命保険でも対象となります。
また個人年金保険は個人年金保険料控除の対象となり、生命保険料控除とはまた別に所得控除を受けることができるのです。
貯蓄型保険のデメリット


貯蓄型保険の説明とメリットについて今までお伝えしてきましたが、次に貯蓄型保険のデメリットについても触れたいと思います。
主なデメリット
戻って黒かねが元本割れ(支払った保険料の総額を下回る)リスクがある
保険料が掛け捨ての保険と比べて高い
保険商品によってはインフレによる影響のリスクがある
以上の3つが主なデメリットです。それぞれを説明しますね。
元本割れのリスクがある
貯蓄型保険のデメリットの1つとして預貯金とは違い、保険会社に支払った保険料よりも解約時に戻ってくるお金が少なくなることがあげられます。
預けたお金に対して受け取るお金が下回ることを元本割れといいます。
繰り返しになりますが、貯蓄保険は預貯金とは違い、いつ解約しても支払った保険料の総額全額が返戻金になるわけではありません。
支払期間満了までのタイミングで解約してしまうとほとんどの場合返戻率が低いのです。
元本割れしないように保険を解約する時にはその時点の返戻率を確認しましょう。





保険料が掛け捨ての保険より高い
貯蓄型の保険は掛け捨ての保険と比べると保険料が高くなります。
どういうことかというと、同じ保障額の保険でも、の掛け捨ての保険で毎月支払う保険料に比べて貯蓄型保険で毎月支払う保険料はかなり高くなるということなのです。
掛け捨ての保険は満期保険金や解約返戻金を保険会社が契約者に支払う必要がないので保険料を安く設定することができます。
ここで気をつけたいのが、必要な保障額を考えた上でその保障額をカバーする貯蓄型の保険料の支払いが高過ぎた場合、貯蓄型の保険に執着しないという事です。



掛け捨ての保険であればもっと安く理想の保証額をかなえることができるかもしれませんよ。
また、低解約返戻金型終身保険という保険もあります。
この保険は保険料支払期間満了までの解約返戻金がグッと下がってしまいますが、その分保険料を安く設定することができる終身保険です。
保険によってはインフレリスクがある
貯蓄型保険の固定金利タイプの保険はインフレのリスクがついて回ります。
契約時点での貨幣価値で支払い満了時の満期保険料や解約返戻金の返戻率が決まってしまいます。
より具体的に説明しますと、契約後にインフレ(物価が急激に高くなり貨幣価値が下がる現象)がおきてしまっても返戻金の金額が貨幣価値によって変わるものではないという事です。
例えば、契約時に30年後に家のリホームを考えて返戻金が大体1000万円だと見通していたとします。
しかし実際30年後にリホームをしようと思って見積もったところインフレの影響でリホームにかかる金額が1500万円かかってしまう。
こういったリスクが特に固定金利タイプの保険商品の場合には起こるという事なんです。
貯蓄型保険が向いている人の特徴


ここまで貯蓄型保険についていろいろな情報をお伝えしてきました。
次はこの貯蓄型保険はどんな人に向いているのかをお伝えしますね。
保険料が戻ってこないことが不満な人
毎月支払う保険料は安くはないですよね。
この保険料がもし、保険が適用されることがないまま満期を迎えたときに、何も残らない、つまり満期保険金や解約返戻金が戻ってこないのが掛け捨ての保険です。
ですからこの『全くお金が戻らない』という事に不満を感じる人には貯蓄型保険が合っているかもしれません。
貯蓄型保険は万一の時に備えつつ、貯蓄というかたちで将来の資金を積み立てることができます。
保険金支払い期間満了が過ぎればほとんどの場合100%以上の返戻金で解約返戻金が受け取れるでしょう。
『全くお金が戻らない』という不満は貯蓄型保険であれば解消で消えるのではないでしょうか。





老後(将来)に貯蓄をしたい人
貯蓄型保険は老後(将来)の資金を作りたい人にも向いている保険タイプだと言えるでしょう。
特に貯蓄をする目的がはっきりしている人にはマッチする保険タイプではないでしょうか。
例えば、老後の資金、個人年金、また学資保険など将来のある時点を見据えて貯蓄したい人にとってはうってつけですね。



貯蓄と共に保険の側面もあるので一石二鳥の保険タイプになりなすね。
貯金をするのが苦手な人
貯金をするのが苦手な人、また貯金をしてのすぐに切り崩して使ってしまうという人が貯蓄をする場合にも貯蓄型保険は向いていると言えます。
貯蓄型保険はもちろん解約することができる保険ですが、貯金を切り崩してしまうよりは面倒です。
更に、保険料支払期間満了時までは変額保険以外はほとんどの場合解約をしてしまうと解約返戻金が元本割れをしてしまうので、支払い続けるモチベーションが上がります。
また貯蓄型保険はあくまで保険商品なので保証はしっかり受けられ、無駄なく万が一に備えることができるのです。



貯蓄型保険が向いていない人の特徴


先ほどとは逆に貯蓄型保険に向かない人はどんな人でしょうか。
- 毎月支払う保険料を抑えてなるだけ大きな保証がほしい人
- 保険の見直しを定期的にしたい人
以上の二つに当てはまる傾向が強い人には貯蓄型保険は向いていないと思います。
保険料を抑えてなるだけ大きな保証がほしい人
毎月支払う保険料をなるだけ抑えておきつつなるだけ大きな保証を受けたいという人は掛け捨ての保険に入るほうが向いていると思います。
同じ保証額を考えたときには貯蓄型保険は掛け捨ての保険よりも保険料が割高になるからです。
また所得があまり多く期待できない人や不安定な職種の人も掛け捨て保険の方がおてごろなので万が一に備えるためには掛け捨ての保険を活用する方が良いと思います。



貯蓄型保険は長期にわたって同じ保険料を毎月支払っていくタイプの保険ですので、毎月確実に支払える金額での契約がおすすめです。
保険の見直しを定期的にしたい人
保険の見直しを定期的にしたい人も貯蓄型保険には向いていないと思います。
先ほどと伝えた通り、貯蓄型保険は長期にわたって将来を見据えた貯蓄と保険なので支払い期間が長期にわたり、途中で保険料の見直しや保証の見直しがほぼできないからです。
例えば死亡保険の掛け捨ての定期保険であれば、一定の期間の死亡保険に加入することにより1年の短期から5年以上の長期にわたって契約時に期間を定める事ができます。
その節目になる年で保険を見直すことが可能なので保険の見直しを定期的にしたい人は掛け捨ての保険の方が貯蓄型保険よりも向いているのではないでしょうか。
まとめ
素人ながら、貯蓄型保険について調べてまとめたのですが、かなり長い記事になってしまいすみません。
素人だからこそ長い記事になってしまったのかもしれませんが、なるべくわかりやすく説明してきました。
少し堅苦しい話になってしまったようにも思いますが、お金が絡む事なので私はいたって真剣です。
しかし、この記事で分からないことがあるようでしたら、私が参考にした1部のWEBサイトを調べてみるのも1つの手かもしれません。
この記事の最初にもお伝えしたように私は保険に関して本当に何も知らなかったのでこの記事を書こうと思いました。
実際に保険に加入しようとするのであれば、私も保険の専門家やフィナンシャルプランナーに相談するでしょう。
保険に興味をもって契約したいと思ったら、加入の相談に行く前にこの記事を読んで専門用語などに免疫をつけておくと良いかもしれません。
もちろん保険の相談場所やフィナンシャルプランナーの方も親切にわかりやすく説明して下さると思いますが、情報を一気にたくさん浴びるより準備をして少し新しく耳にする情報を減らしておくのも大事だと思います。
長文を最後まで読んでいただき本当にありがとうございました。
こちらに「一人暮らしの貯金」に関する記事と「一人暮らし節約法」に関する記事があるのでよろしければ併せてご覧ください↓↓↓






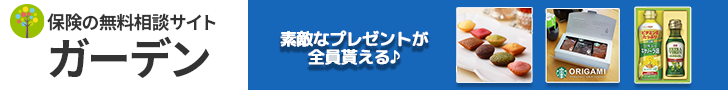
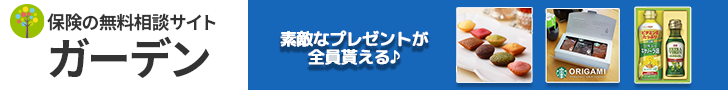
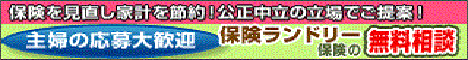
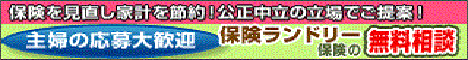

コメント